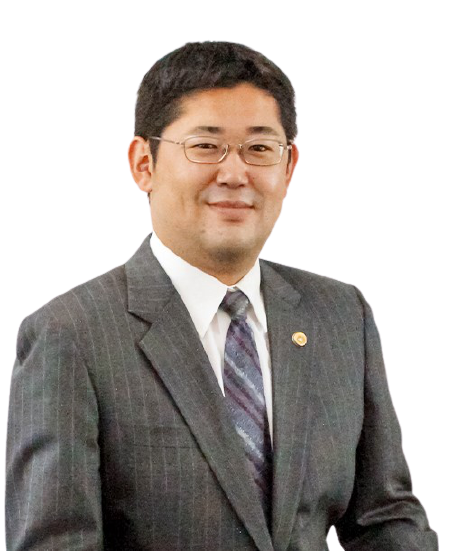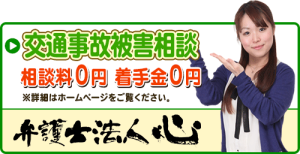ブログ
無保険車傷害保険について
名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、自動車保険の無保険車傷害保険についてお話します。
自動車事故の加害者が、必ず任意保険に加入している・・・(続きはこちら)
証拠保存の重要性
名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、交通事故の証拠保存の重要性についてお話します。
交通事故に限らず、賠償金の請求には、裏付けとなる証・・・(続きはこちら)
自賠責保険の回答書
名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、自賠責保険の回答書について説明します。
自賠責保険に対して治療費等を被害者請求した場合、損害保険料率・・・(続きはこちら)
被害者請求の注意点
名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、自賠責保険への被害者請求の注意点についてお話します。
自動車事故が原因でお怪我をされた場合、医療機関・・・(続きはこちら)
駐車場内における事故の注意点
名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、駐車場内での事故の注意点をお話します。
駐車場内での交通事故は、道路上の事故よりも慎重な対応が必要となり・・・(続きはこちら)
交通事故と障害年金
名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、交通事故と障害年金の関係についてお話します。
交通事故により、被害者が重大な傷害を負ってしまうことが・・・(続きはこちら)
交通事故実務と被害者の方の思いの乖離
名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、交通事故における被害者の方の思いと実務の乖離についてお話します。
弁護士として交通事故事件に関わって・・・(続きはこちら)
運転の際はご注意を
名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
交通事故のご相談・ご依頼をいただいていると、様々な事故の話を耳にします。
交通事故は、脇見、ぼんやりしていた・・・(続きはこちら)
脊柱以外の体幹骨の障害
名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、脊柱以外の体幹骨の障害について説明します。
1 脊柱以外の体幹骨の障害
自賠責保険の後遺障害認定・・・(続きはこちら)
圧迫骨折の注意点
名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、圧迫骨折の注意点について説明します。
1 交通事故と圧迫骨折
激しい勢いでの追突事故に遭う等した・・・(続きはこちら)